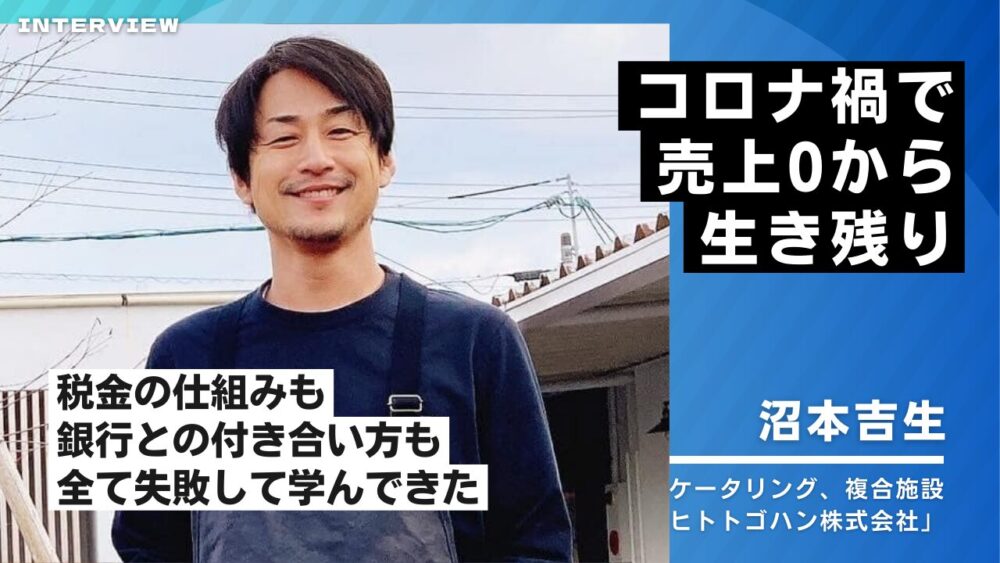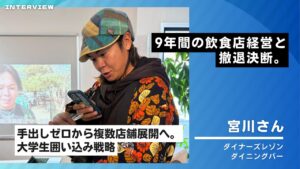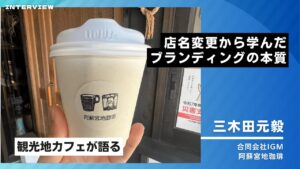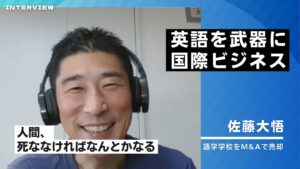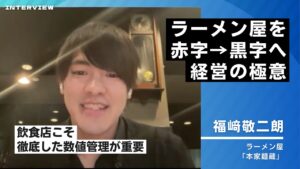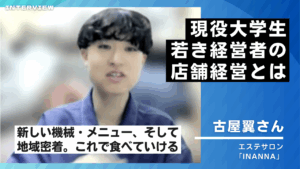飲食店経営は夢のある仕事ですが、特に多店舗展開となると様々な課題が立ちはだかります。今回は岡山県の中山間地域で「ヒトトゴハン株式会社」を運営する沼本吉生さんに、ケータリング事業から始まり、廃校を活用した複合施設の運営まで、その壮絶な経営体験をお聞きしました。
コロナ禍での苦境や事業拡大の判断、資金繰りの問題など、店舗経営者ならではの貴重な経験から学べるポイントを紹介します。
店舗経営者プロフィール

沼本吉生さんは、岡山県の中山間地域で「ヒトトゴハン株式会社」を経営するベテラン飲食事業家です。10年前にケータリング事業から創業をスタート。現在は廃校を活用した複合施設を拠点に、複数の事業を手がけています。
起業のきっかけと紆余曲折の道のり
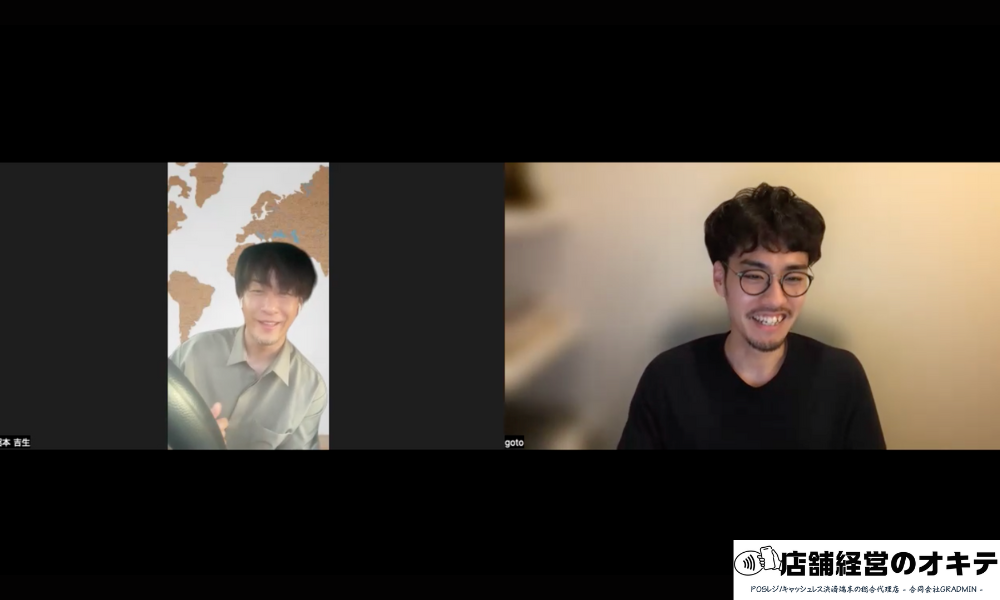
沼本さんの創業ストーリーは、決して順風満帆ではありませんでした。27歳まで東京でサラリーマンをしていた沼本さんは、料理の仕事に興味を持ったものの、体調を崩して岡山の実家に戻ることに。
ーー現在までカフェ、ケータリング、廃校利活用の三事業を経験されてきたとお聞きしました。それぞれの開業のきっかけを教えていただけますか?
「体調を崩して、ほぼ寝たきり状態で岡山の田舎に戻りました。人口4万人ほどの中山間地域です。車の免許がなかったので、30歳近くになると地元では就職も難しく、コンビニのバイトにも落ちる状況でした」
そこで沼本さんが始めたのが、料理のケータリング事業。当時は車の免許がないという弱みを逆手に取り、「迎えに来てもらったら安くする」という独自のサービスを考案しました。
「最初は自宅から始めて、周りの協力もあって少しずつ広がっていきました。売上も年々徐々に増えていきました」
事業拡大の決断と多店舗展開への道
ケータリング事業が軌道に乗り始めた沼本さんは、地域の市役所とのつながりを深め、新たな事業展開を模索します。
「市役所が地域では一番大きな組織だったので、そこで仕事をもらえないかと考えました。地域振興の企画書を出したり、料理教室の講師をしたりして、ネットワークを広げていったんです」
その結果、廃校活用事業に関わるチャンスを得た沼本さん。現在までに4つの廃校施設に関わってきました。
- 廃校となった小学校:現在のセントラルキッチンとして使用している給食室
- 近くの保育園:地元住民とのデイサービスとしての交流施設
- 山の上の小学校:リノベーションした複合施設(カフェも併設)
- 隣市の大型幼稚園:リノベーションしたテナント誘致型の複合施設
「料理を作ることから『コト』を作る仕事に発展させたかったんです。行政と組んで何かできないかと考えていました」
そしてコロナ禍となる前年の2019年に、1つ目の廃校利用複合施設『UEDAVILLAGE』をオープン。

しかし、翌年にコロナ禍となり、過去最高の売上をあげていたにも関わらず、従業員と地域住民の安全を第一にコロナ禍中は閉鎖。(現在は運営を他者に任せ自身は撤退)
コロナ禍での苦境と立て直し
順調に事業を拡大していた沼本さんを襲ったのが、コロナ禍。特に山の上にあった複合施設は、若者をターゲットにしていたため、大きな打撃を受けます。
「山の上の施設は人口300人ほどの高齢者が多い集落にありました。そこに20代の市外の若い女性をターゲットにしたマーケティングをしていたので、コロナとの相性が最悪でした。若い人たちが市外から来ることで感染リスクへの懸念もあり、一時閉鎖せざるを得なくなりました」
コロナ禍での売上激減により、資金繰りにも苦労。クラウドファンディングやコロナ融資、助成金を活用しながら、なんとか事業を存続させました。
「コロナ開始から1ヶ月後にクラウドファンディングを実施して支援を仰ぎました。同時にコロナ融資を最大限に活用し、国の助成金や補助金で食いつなぎました」
最も厳しかった時期と乗り越え方
ーー事業は順調なのにコロナ渦で道が途絶えるのは悔やまれますね。壮絶な日々だったかと思うのですが、これまでの経営の中で、最も厳しかった時期はいつ頃でしたか?
沼本さんにとって最も厳しかった時期は、コロナ融資の返済が始まり、社会保険の支払い猶予も終わった頃だったといいます。
「売上は増えていたのに、返済でキャッシュはなく、税金も分納で返済する状態でした。朝5時に起きて夜19時まで働き、現場にも出て、マネジメントもして、資金繰りもして…自律神経も乱れ、精神的にも追い込まれました。」
そして最も辛かったのは、従業員を解雇せざるを得なかった時だと振り返ります。
「一番苦しかったのは、コロナ中に雇っていた男性従業員を解雇したときです。家族がいる従業員だったので何とか守りたかったのですが、資金ショートが見えてきて、申し訳ないけれど解雇せざるを得なくなりました。力不足で頭を下げて謝るのが一番辛かったですね」
しかし沼本さんは、解雇した元店長にカフェの経営を譲り、新たな道を開くことで、自分なりの「償い」を果たしました。
「解雇はしましたが、店舗を事業譲渡する形で彼の独立を支援しました。損益分岐点も超えていた黒字店舗だったので、売上を増やせば彼の収入も増えます。彼も独立志向だったので、ある意味ピンチをチャンスに変えることができました」
そんな沼本さんは現在「Sense Tsuyama」という複合施設を運営中です。

『Sense Tsuyama』


当施設はキッズデザイン賞も受賞した、子どもや子どもの産み育てに配慮された施設です。


多店舗経営で学んだ教訓
ーー経営を続ける中で、以前と比べてご自身の考え方に変化はありましたか?特に人間的な面において。
1. 固定収入と変動収入のバランス
沼本さんが経営を通じて学んだ重要な教訓の一つが、収入源の多様化です。
「コロナを経験して、予約制や来客を待つフロー型のビジネスモデルだけでは不十分だと気づきました。ストック型の家賃収入など固定収入があるビジネスモデルも持つ必要があります」
そこで沼本さんは、隣町の大型幼稚園をリノベーションした際に、自社だけの店舗ではなく、テナントを入れて家賃収入も得られる形態を選択しました。
2. 「当たり前」を徹底する大切さ
多店舗を運営する中で、沼本さんは店舗運営の基本を見直すきっかけも得ました。
「ケータリング時代はおまかせメニューだったのでアドリブの部分が多かったのですが、固定メニューのカフェでは、店舗として『当たり前のことを当たり前に徹底する』ことが重要だと気づきました。清掃、接客、仕込み、調理、サービス、広告宣伝など基本的なことをきちんとやり続けることが、実は一番難しいんです」
3. お金の使い方・管理の重要性
資金繰りに苦労した経験から、細部にわたる資金管理の重要性も学んだと言います。
「銀行との付き合い方を全く知らず、言われるままに借り入れをしていました。実は銀行同士で金利の相見積もりができることや、必要以上に借りると逆にコストがかかることなど、経営の基本を知らなかったんです」
また、日々の支払いをポイント還元のあるクレジットカードで行うなどの工夫も、後から気づいたといいます。
「年間の支払総額が2,000万円あれば、1%のポイント還元でも20万円。これが3年で60万円になります。当たり前のように捨てていたお金がたくさんありました」
これから開業する方へのアドバイス
ーーこれから開業を考えている方々へのアドバイスをお聞かせいただけますか?
沼本さんが、これから店舗経営を始める方に向けて伝えたいアドバイスは次の3つです。
1. 固定費を抑えること
「店舗の場合、家賃などの固定費をいかに下げるかが重要です。家賃は交渉できるものですし、立地にこだわらなくてもGoogleマップなどを活用すれば集客できる時代です。廃校のような極端に安く借りられる場所を探すのもおすすめです」
沼本さんは、自身も現在テナントの大家をしている経験から、家賃交渉の重要性を強調します。「家賃って結構あってないようなものなんですよね。基本的には交渉ができて、地価が上昇しない限りは、建物の価値はどんどん下がるものなので安くなるものなんですよね」
これは創業時に知っておくべき重要なポイントで、特に地方では立地にこだわらず、コストを最小限に抑える工夫が長期的な経営安定につながると言います。
2. お金の流れを最適化する
「支払いはすべてポイントが貯まるクレジットカードを使う、必要最低限の借入にする、補助金や助成金を積極的に活用するなど、お金の流れを最適化することも大切です」
補助金については「創業して3年目ぐらいまで補助金全然知らなくて使ってなかった」と言い、機会損失の大きさを指摘します。
3. 採用とチーム作りを慎重に
「年間粗利が1,000万円を超えるまでは人を雇わない方がいいでしょう。また、雇う際は使用期間中にしっかり見極め、会社のルールを明文化して、コミュニケーションができる人材を選ぶことが重要です」
沼本さんは法人設立初期に「何も知らないのに二人雇っちゃって」と振り返り、一人会社の状態で「社員二人分頑張って稼ぐみたいな」状況になってしまったと言います。
具体的なチーム作りの工夫として、「七つのルール」を制定し、入社時に明確に説明する取り組みも紹介してくれました。「悪口言わないとか、失敗は追求せずに問題改善とカバーすることに全力注ぐとか、多様性を大事にすること」などのルールを設け、「これをやってる人とは絶対仕事はもう無理だな」というものをまとめ、「できない人は解雇理由にもさせていただきます」と採用時に伝えるそうです。
>>ヒトトゴハンの7ルールはこちらよりご確認いただけます
この明確なルール設定により、チームのコミュニケーションがスムーズになり、後々のトラブル防止にもつながっているとのことです。
多店舗経営で失敗しないための7つのポイント
沼本さんの経験から、多店舗経営で失敗しないためのポイントをまとめました。
- 収入源を多様化する:フロー型(予約制)とストック型(家賃収入など)をバランスよく持つ
- 基本を徹底する:「当たり前のことを当たり前に」行うことの継続が成功の鍵
- 固定費を最小限に:家賃交渉や立地にこだわらない発想で初期コストを抑える
- 資金管理を徹底する:ポイント還元などの小さな工夫が長期的には大きな差になる
- 銀行との賢い付き合い方:金利交渉や必要最低限の借入を心がける
- 人材採用は慎重に:採用基準を明確にし、コミュニケーション能力を重視する
- 複数の収益源を持つ:ケータリング、カフェ、施設運営など、複数の事業を持つことでリスク分散を図る
編集後記



沼本さんのインタビューを通して、多店舗経営の難しさと同時に、その可能性も見えてきました。特に印象的だったのは、ピンチをチャンスに変える柔軟な発想と、「当たり前のことを当たり前に」という基本への回帰です。
コロナ禍という前例のない危機を乗り越え、さらに事業を発展させた沼本さんの経験は、これから店舗経営を始める方だけでなく、すでに経営している方にとっても大きな指針となるでしょう。単なる「成功体験」だけでなく、失敗や苦労を乗り越えてきたリアルな体験だからこそ、その言葉には重みがあります。
沼本さんが言うように、お金の流れを最適化し、基本を徹底し、そして何より自分自身の情熱を失わないこと。それが多店舗経営で成功するための「道しるべ」なのかもしれません。
本記事は実際の店舗経営者へのインタビューをもとに作成しています。