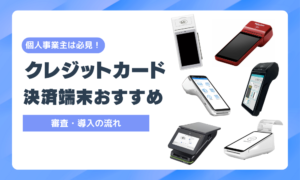キャッシュレス決済の普及に伴い、「d払い」の導入を検討している事業者さまも多いのではないでしょうか。
しかし、実際にd払いを導入するとなると「どのような手数料がかかるのか」「本当に自社のビジネスに合っているのか」といった不安や疑問が出てくるものです。
そこでこの記事では、d払いの導入にかかる手数料の種類や金額、メリット・デメリットについて詳しく解説しています。
- d払いの導入にかかる初期費用と各種手数料
- d払いを導入するメリット
- d払いを導入する前に考慮するべき注意点とデメリット
- 利用者側が負担する可能性のある手数料
ぜひ最後までご覧いただき、d払いを導入する際の参考にしてください。
d払いの導入にかかる手数料は?基本情報を徹底解説
d払いの導入・運用には、いくつかの手数料が発生します。
実際にd払いの導入を検討する際は、発生する手数料をよく理解したうえで検討を進めましょう。
ここでは、d払いの基本的なサービス概要と、導入時に考慮するべき主な手数料について解説します。
- d払いとは?サービスの概要と特徴
- d払いの導入にかかる手数料の種類
d払いとは?サービスの概要と特徴
d払いとは、NTTドコモが提供しているキャッシュレス決済サービスです。
ドコモの回線契約がなくても、dアカウントを作成すれば利用可能で、QRコードやバーコードを読み取るだけで簡単に支払いが完了します。
d払いの利用によって貯まったdポイントは各種支払いに利用できるため、利用者にとっては、d払いを利用するほどお得になる決済方法です。
d払いには、以下の3種類の支払方法が用意されています。
- 電話料金との合算払い
- 銀行口座などからチャージした、d払い残高からの支払い
- クレジットカード
また、2020年9月より、ドコモが提供する「d払い」と、メルカリが提供する「メルペイ」のQRコードが統一されました。
共通QRコードの開始により、d払いを導入する事業者は、ひとつのQRコードでd払いとメルペイの2種類の決済方法に対応できます。
d払いの導入にかかる手数料の種類
d払いの導入にかかる手数料は、大きく分けて以下の3つに分類されます。
- 初期費用
- 決済手数料
- 振込手数料
これらの手数料を正しく理解して、導入・運用にかかるコストを把握し、適切な経営判断を行いましょう。
初期費用
d払いは、初期費用と月額固定費が基本的に無料で導入できるサービスです。
ただし、利用者がスマートフォンに表示したQRコードを店舗側が読み取る「ストアスキャン方式」の場合は、コードを読み取るための決済端末が必要です。
キャンペーンなどで決済端末にかかる費用が無料になるケースもありますが、多くの場合、決済端末費用がかかるものと考えておきましょう。
一方で、店舗に掲示したQRコードを顧客がスマートフォンで読み込む「ユーザースキャン方式」の場合は、決済端末費用はかかりません。
決済手数料
決済手数料とは、利用者がd払いを利用した際に、加盟店が支払わなければならない手数料のことです。
d払いとメルペイの共通QRコードを導入した場合は、1回の決済につき2.6%の決済手数料がかかります。
決済手数料を差し引いた金額が、店舗の口座に振り込まれる仕組みです。
ただし、2023年12月1日より、申込日の月を含む最大6か月の間、d払いの決済手数料が無料になるキャンペーンが実施されています。
最大6か月手数料無料キャンペーンは、メルペイとの共通QRコードを新規に導入する加盟店が対象です。
なお、キャンペーンの終了日については、終了日が決定次第、d払い公式サイトで告知される予定です。
参考:d払いで実施のお得なキャンペーン|キャッシュレスならd払い(外部サイト)
振込手数料
d払いにおける振込手数料とは、d払いによる売上金が、店舗の口座に振り込まれる際に発生する手数料のことです。
原則として、d払いの振込手数料は無料ですが、1万円未満の入金については200円(税込)の振込手数料がかかります。
なお、売上金が1万円以上になるまで繰り越すことも可能です。
また、d払いの入金サイクルは、毎月1回または2回から選べます。
月2回の入金サイクルを選択した場合でも、入金予定額が1万円以上であれば振込手数料はかかりません。
手数料がかかってもd払いを導入するメリット
上述の通り、d払いの導入には決済手数料をはじめとした、さまざまな手数料が発生します。
それでもなお多くの事業者がd払いを導入する理由は、手数料の負担を上回るメリットがあるためです。
ここでは、d払いの導入によって期待できる具体的なメリットを詳しく解説します。
手数料がかかってもd払いを導入する主なメリットは次の通りです。
- 集客力の向上が期待できる
- クレジットカードを持っていない人も利用できる
- 業務効率化が期待できる
- 加盟店向けのキャンペーンを利用できる
- 万全のセキュリティ対策で安心して利用できる
集客力の向上が期待できる
d払いを導入する最大のメリットは、2024年3月末時点で約1億人にのぼるdポイントクラブ会員へのアプローチが可能になる点です。
d払いの利用によって貯まるdポイントは、日本国内でも有数の規模を誇る共通ポイントサービスのひとつです。
利用者向けのd払いアプリでは、クーポンの配信やメッセージの送信といった、独自の販売促進施策が提供されており、店舗側は効率的な集客が可能になります。
さらに、d払いはメルペイとの共通QRコードに対応しているため、d払いユーザーだけでなくメルペイユーザーを取り込むことも可能です。
フリマアプリ「メルカリ」の月間利用者数は、2023年6月時点で2,000万人を超えています。
d払いとメルペイという二つの決済方法に対応することで、dポイントクラブとメルカリの豊富な会員数へ向けた集客が可能です。
参考:スマホ決済を導入するならd払い&メルペイ|キャッシュレス決済ならd払い(外部サイト)
クレジットカードを持っていない人も利用できる
d払いはクレジットカードを持っていない人でも利用できる便利なキャッシュレス決済サービスです。
d払いには、以下の3種類の支払方法が用意されています。
- 電話料金との合算払い
- 銀行口座などからチャージした、d払い残高からの支払い
- クレジットカード
ドコモ回線契約者であれば、月々の電話料金との合算払いが可能なため、クレジットカード情報を登録せずにd払いを利用できます。
また、ドコモ回線を利用していない人でも、銀行口座またはセブン銀行ATMから事前にチャージしておくことで、d払い残高からの支払いが可能です。
学生やクレジットカードを持たない人にとって、現金チャージができるd払いは利便性が高いキャッシュレス決済サービスだといえるでしょう。
業務効率化が期待できる
d払いの導入によって、店舗運営における業務の効率化が期待できます。
キャッシュレス決済であるd払いを導入することで、現金の取り扱いを減らすことが可能です。
これにより、レジでのお釣りの準備や現金管理、レジ締め作業にかかる時間と労力を大幅に削減できます。
特に、混雑時のレジ業務がスムーズになることで、顧客の待ち時間短縮にもつながり、結果として顧客満足度の向上も期待できるでしょう。
また、不特定多数の人が利用する店舗において、日々の売上管理は、負担が大きい業務のひとつです。
しかし、d払いの販売データは自動的に記録され、必要な時に簡単にダウンロードできるため、売上管理や経営戦略の立案を効率化できます。
加盟店向けのキャンペーンを利用できる
d払いでは、加盟店向けの各種キャンペーンが不定期で実施されています。
これらのキャンペーンを活用できれば、本来発生するd払いの導入手数料や決済手数料の負担を一時的に軽減することが可能です。
たとえば、2025年4月現在では、通常なら2.6%かかる決済手数料が、最大6か月間無料になるという、d払いを新規で導入する店舗向けのキャンペーンが実施されています。
また、過去には、特定の加盟店でd払いを利用すると、通常よりも多くのdポイントが付与されるキャンペーンが展開されていました。
こうしたキャンペーンは消費者の関心を集めやすく、期間中の来店数や売上アップが期待できます。
d払いで実施されている各種キャンペーンは変更・終了の可能性もあるため、ドコモの最新情報を確認しましょう。
万全のセキュリティ対策で安心して利用できる
d払いは、高度なセキュリティ体制が整備されており、店舗・利用者の双方が安心して利用できる決済手段です。
キャッシュレス決済において、不正利用や情報漏洩は特に不安視されやすいポイントですが、d払いはその対策が徹底されています。
具体的な対策として、d払いでは以下のようなセキュリティ対策が採用されています。
- 24時間365日不正モニタリングを実施
- 二段階認証などの不正アクセス防止機能に対応
- 不正利用された場合の補償制度
d払いの万全なセキュリティ対策にもかかわらず、不正利用の被害を受けた場合は、ドコモが原則として全額を補償してくれます。
万が一不正利用が発生した場合でも、加盟店側の損失リスクを軽減できるという安心感は大きな魅力です。
d払いを導入する前に考慮するべき注意点とデメリット
d払いの導入は多くのメリットがある一方で、導入する前に考慮するべき注意点やデメリットも存在します。
実際に導入を検討する際は、これらの点も踏まえて総合的に判断することが重要です。
d払いを導入する前に考慮するべき注意点とデメリットは以下の通りです。
- インターネット環境が必要
- 決済手数料を負担しなければならない
- d払いを利用していないユーザーがいることも考慮する
これらのデメリットを事前に把握しておくことで、d払い導入後のトラブルを回避し、スムーズな運用が可能になります。
それぞれの注意点とデメリットについて詳しく見ていきましょう。
インターネット環境が必要
d払いの導入には、安定したインターネット環境が欠かせません。
インターネット環境は、ほかのキャッシュレス決済サービスと同様に、オンラインでの認証や決済処理を行う際に必要です。
インターネット環境が不安定な場合は、決済処理に時間がかかったり、エラーが発生したりする可能性があります。
ただしd払いでは、2025年1月29日より、インターネットに接続していなくても支払いが可能になる新機能が追加されました。
この新機能は、利用者がスマートフォンに表示したQRコードを店舗側が読み取る「ストアスキャン方式」でのみ利用できます。
時間や月ごとの利用上限回数が定められていますが、事前の設定などは不要で、通信障害時などでも決済用のバーコードやQRコードの表示が可能です。
決済手数料を負担しなければならない
d払いを導入するうえで避けて通れないのが、決済手数料の負担です。
d払いでは、1回の決済につき2.6%の決済手数料がかかります。
ほかのキャッシュレス決済サービスと比較すると、d払いの決済手数料は決して高くありませんが、利益率が低い商品を扱う店舗にとっては無視できない負担です。
2025年4月現在では、d払いの利用による決済手数料が、最大6か月間無料になるというキャンペーンが実施されています。
そのため、現在d払いの導入を検討している場合は、早めの導入がおすすめです。
導入後7か月目以降や、キャンペーンが終了してからの導入には、通常の決済手数料が継続的にかかりますので注意してください。
d払いを利用していないユーザーがいることも考慮する
d払いは非常に便利な決済手段ですが、すべての顧客がd払いを使えるわけではありません。
特に、高齢者層を中心としたスマートフォンに不慣れな人の中には、利用のハードルが高いと感じる人も多いでしょう。
また、さまざまなキャッシュレス決済サービスが幅広く展開されている中で、d払い以外の決済手段をメインで使っている顧客も多くいます。
d払いの導入を検討する際は、自店舗の主な顧客層がどのような決済手段を好むのかを事前にリサーチしておくことも大切です。
d払いの利用者側が負担する手数料はある?
「d払いの導入を検討しているけれど、利用者側に手数料が発生すると顧客から敬遠されるのでは?」と心配されている事業者さまも多いのではないでしょうか。
基本的に、店舗でd払いを利用して決済を行う際は、利用者が負担する手数料はありません。
しかし、d払いを利用するいくつかのケースでは手数料が発生することもありますので注意が必要です。
d払いで利用者側が負担しなければならない手数料が発生するケースは以下の通りです。
- d払い残高から払い戻す際に出金手数料が発生する
- メルカリでd払いを利用すると100円以上の決済手数料が発生する
- 失効したd払い残高の返金に550円の返還手数料が発生する場合がある
それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
d払い残高から払い戻す際に出金手数料が発生する
d払いでは、d払い残高から任意の銀行口座やセブン銀行ATMに払い戻すことが可能です。
ただし、銀行口座かセブン銀行ATMに払い戻す場合は、1回あたり110円から220円(税込)の手数料がかかります。
また、ドコモ回線契約者の場合は、携帯料金に充当する形でd払い残高から出金することも可能です。
携帯料金に充当する形でd払い残高から払い戻す場合、手数料はかかりません。
メルカリでd払いを利用すると100円以上の決済手数料が発生する
フリマアプリの「メルカリ」では、d払い決済が可能です。
ただし、メルカリでd払い決済を行うと、1回の決済ごとに100円以上の手数料が発生します。
このとき発生する手数料は、支払金額に応じて変動します。
なお、dカードで支払う場合や、全額をdポイントで支払う場合、手数料はかかりません。
参考:メルカリの手数料 – メルカリ スマホでかんたん フリマアプリ(外部サイト)
失効したd払い残高の返金に550円の返還手数料が発生する場合がある
d払いでは、失効したd払い残高に対して返金手続きを行う場合に、550円(税込)の返還手数料が発生することがあります。
利用者が、ドコモ回線の解約やクーリングオフなどの手続きを行った場合、d払い残高が失効します。
失効したd払い残高は、利用していたdアカウントでd払い残高の利用登録を行えば、返金してもらうことが可能です。
ただし、dアカウントの削除またはドコモが定める方法以外で返金してもらう場合は、550円(税込)の返還手数料が発生します。
d払いの導入手数料を正しく理解して、ビジネスに最適な決済手段を選ぼう
この記事では、d払いの導入にかかる手数料の種類や金額、導入のメリット・デメリットについて解説しました。
d払いの導入にかかる初期費用と各種手数料
- d払いの導入には「初期費用」「決済手数料」「振込手数料」という3つの手数料がかかる
- 初期費用は基本的に無料だが、ストアスキャン方式の場合は決済端末が必要
- 決済手数料は、1回の決済につき2.6%の手数料負担が発生する
- 振込手数料は原則無料だが、1万円未満の入金については振込手数料が発生する
d払いを導入するメリット
- 店舗側は、集客力の向上や業務効率化が期待できる
- クレジットカードを持っていない人も利用できる
- 万全のセキュリティ対策により、店舗・利用者の双方が安心して利用できる
d払いを導入する前に考慮するべき注意点とデメリット
- スムーズな会計処理を行うためには、安定したインターネット環境が必要
- 決済手数料の負担が継続的に発生する
- d払いを利用していないユーザーがいることも考慮する必要がある
利用者側が負担する可能性のある手数料
- d払い残高から払い戻す際に110円から220円(税込)の出金手数料が発生する
- メルカリでd払いを利用すると100円以上の決済手数料が発生する
- 失効したd払い残高の返金に550円の返還手数料が発生する場合がある
d払いを導入するうえで、手数料の負担は避けて通れません。
導入を検討する際は、導入によって発生する手数料と、期待できるメリットとのバランスを考慮したうえで、総合的に判断することが大切です。
d払いの導入・運用に伴う手数料を正しく理解して、自社のビジネスに最適な決済環境を構築しましょう。