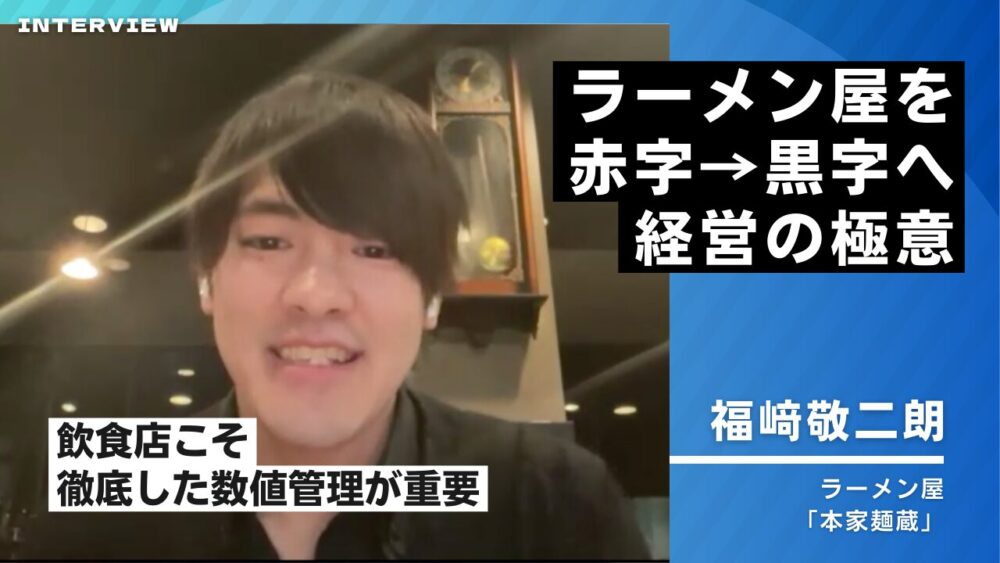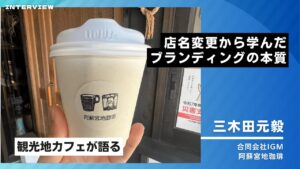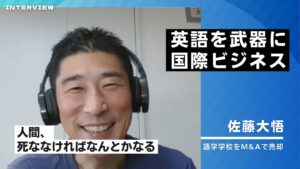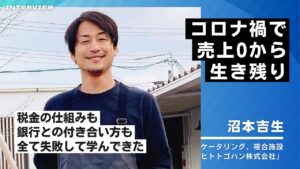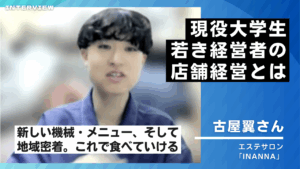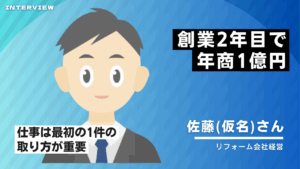ラーメン業界は参入障壁が低い一方で、競争が激しく撤退するお店も多いのが現実です。全国にある何万軒ものラーメン店の中で、長く愛され続けるお店になるためには何が必要なのでしょうか?
今回は北海道伊達市で8年間ラーメン店を経営する福﨑さんにお話を伺いました。前オーナーから店舗を引き継ぎ、赤字だった店舗を黒字化させた経験から、ラーメン店開業で失敗しないためのポイントを語っていただきました。
店舗経営者プロフィール
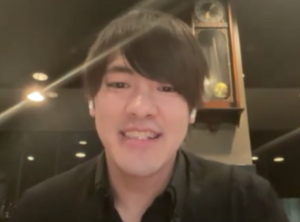
名前:福﨑敬二朗さん
店舗:本家麺蔵
場所:北海道伊達市
経営歴:8年(前オーナーの下で3年半修行後、店舗を引き継ぐ)
SNS:https://x.com/honkemenzo
サラリーマンから店主へ – ラーメン店を引き継いだ経緯
両親が居酒屋を経営していたこともあり、飲食業は福﨑さんにとって身近な存在でした。いったんは会社員として就職したものの、「枠組みの中でしか仕事ができない」「頑張ってもお給料の上限が決まっている」という窮屈さを感じていたそうです。
「自分で事業をしたいという思いがあったときに、知り合いからラーメン屋が人手不足だから働かないかと声をかけてもらったんです」
そこから約3年半、前オーナーの下で修行を積み、店舗を引き継ぐ形で独立。しかし、その引き継ぎ方は一般的な事業継承とは少し違っていました。
「正式な事業継承ではなく、本当に軽い感じで引き継ぎました。お店も大きくないので、しっかりとした契約書も交わしていません」

赤字店舗からの再建 – 黒字化までの道のり
店舗を引き継いだ当初、お店は赤字経営だったといいます。
――店舗を引き継いだ当初の状況はいかがでしたか?

「おそらく順風満帆に経営していたわけではないと…思います」
そんな状況から、どのようにして黒字経営に転換したのでしょうか。
――赤字から黒字に転換できた要因は何だと思いますか?
福﨑さんは以下の4つにあると答えました。
- 意識の変化が最大の転機に
- データに基づく数値管理の徹底
- コストパフォーマンスで差別化
- メニュー表のビジュアル改善で客単価アップ
1. 意識の変化が最大の転機に
「前のオーナーの下で働いていた時は雇われでお給料をもらいながら働いていたので、もちろん仕事はきちんとしていましたが、自分で独立してやってみるというのは気持ちが全然違いました」
独立後は、これまで気にしていなかった細かいところまで目が行くようになったといいます。
「ドアの汚れ一つ、スタッフのお客さんへの接し方、ラーメンを運ぶ時のどんぶりの置き方まで、本当に細かいことが気になるようになりました」

私も話を聞きながらラーメンを運ぶ時のどんぶりの置き方、テーブルの清掃の工夫(アルコールスプレーの飛沫が隣の席に飛ばないようにする)などを徹底しているラーメン屋はリピートしたいなと思いました!
2. データに基づく数値管理の徹底
「売上だとか原価率だとか、仕入れ先とか、そういった細かいところも勉強するようにしました。飲食店なら原価率は平均30%くらいと言われていますが、そういった標準的な数字と照らし合わせて、うちはどうかとデータを意識しながらやるようになりました」
3. コストパフォーマンスで差別化
店舗を引き継いだ当初は「ワンコインラーメン」と称して500円でラーメンを提供していました。現在は700円に価格改定したものの、それでも地域では最安値とのこと。
――他店との差別化のために工夫していることはありますか?
「ランチの予算は限られていて、1,000円を上限になかなか足してぶるっていうラインがあるんです。そのラインを意識して、うちはラーメン700円と半チャーハン300円のセットで1,000円で提供しています。他のラーメン屋さんだと1,200円から1,300円するので、コストパフォーマンスが強みです」
4. メニュー表のビジュアル改善で客単価アップ
――売上・集客アップのために効果があった取り組みはありますか?
「引き継いだ時のメニュー表は写真が載らず、文字だけがバーっと書いてあるようなものでした。自分で写真を撮ってメニュー表に差し込んだところ、客単価が100円から150円ほどアップしました」


「一日100人前後のお客さんがいると、単純に15,000円ほど売上が変わってくる計算になります」
リピーターを増やすための工夫
――リピーターを増やすために何か特別な取り組みはしていますか?
1. 公式LINEを活用したスタンプカード
「公式LINE上でスタンプカードを使えるようにして、3ポイントたまったらトッピング無料、5ポイントで半チャーハン無料などのサービスを提供しています」
「スタンプカードもいきなり5ポイントで半チャーハン無料、10ポイントでラーメン無料だけだと、お得感が弱いと感じました。3回行ったらトッピング無料、さらに2回来れば半チャーハン無料で食べられるという風に、行きやすく、行く動機を提供することが大事だと思っています」
2. 定期的なクーポン配信
「公式LINEで定期的にクーポンを配信しています」
公式LINEの運用は外部に任せているのかとお伺いしたところ、なんとご自身で運営されているとのこと。通常営業だけでなく、LINEの運用からお店の清掃まで、とことんアグレッシブです。



本インタビューもなんと営業終了後の夜21時から引き受けてくださりました。お忙しい中でもご対応いただき感謝です。
ラーメン店経営で直面した課題
――ラーメン店経営で特に大変だったことや課題は何ですか?
1. 季節による売上の変動
「1月、2月が売上が目立って低いです。年末年始でお金を使ったから出し渋るということもあるかもしれません。また、北海道なので雪が降ると足が鈍くなり、天候にも左右されます」
2. 競合との差別化
「伊達市内には競合が9店舗か10店舗あるので、競争は激しいです」
3. 人材育成の必要性
――今後の店舗経営について考え方に変化はありましたか?
「最初は何でも自分でやらなきゃという意識が強かったのですが、長く続けていくと全部自分一人では回らなくなります。店を任せられる人材を育成していくことが大事だと感じています」
これからラーメン店を開業する人へのアドバイス
――これからラーメン店を開業する人へのアドバイスをお願いします


「ラーメン屋さんは参入障壁が低い分、競合も激しく、撤退するお店も多いです。根気強く続けていくことが大事です。すぐに諦めないで、いろんな人の協力を得ながら、アドバイスを聞きながら、改善を繰り返すことが大切です」
――店舗経営で絶対に身につけるべきスキルは何ですか?
必ず習得すべきスキル:数値管理
「数値管理の勉強は必須です。売上や原価、利益がどうやったら出るのか、そういった仕組みを理解することが重要です。お店の売上が下がってきた原因は、結局数字としてのデータに現れます。その数字を見て、どこが悪いのかを突き止めて改善を繰り返していかないと良くなっていきません」
POSレジ・キャッシュレス決済について
――お店ではどのようなPOSレジやキャッシュレス決済を導入していますか?
福﨑さんのお店では、リクルートの「エアレジ」(現:Airレジ)を利用しているとのこと。
「iPadを使って、QR決済やカードなど全部対応できるようになっています。POSシステムで調べた時に最初に出てきて、やりやすそうだし初期費用も安く抑えられそうだったので選びました」
※当サイトでは、エアレジをはじめとする各種POSレジ・キャッシュレス決済端末の詳細情報を掲載しています。詳しくはPOSレジを比較したおすすめ記事をご覧ください。
まとめ:ラーメン店開業で失敗しないために
- 意識改革: オーナーとしての責任感と細部への気配りが重要
- 数値管理: 売上・原価率・利益などのデータを常に分析する習慣をつける
- 差別化戦略: 競合の多いラーメン業界で独自の強みを見つける(例:コストパフォーマンス)
- 視覚的訴求: メニュー表に写真を入れるなど、客単価アップのための工夫をする
- リピーター獲得: LINEなどを活用した顧客囲い込み戦略を実施する
- 人材育成: 自分一人で全てをやろうとせず、店を任せられる人材を育てる
- 継続力: 簡単に諦めず、根気強く改善を続ける
ラーメン店の開業は夢があり魅力的ですが、厳しい現実も待ち受けています。しかし、福﨑さんのように地道な努力と改善を積み重ねることで、愛されるお店を作ることは可能です。数値管理の基本をしっかり押さえ、お客様の心をつかむ工夫を続けていくことで、失敗を回避し長く続くラーメン店を経営することができるでしょう。
編集後記



今回、北海道伊達市で8年間ラーメン店を経営されている福﨑さんにお話を伺いました。インタビューを通して特に印象的だったのは、経営者としての「気づき」の重要性です。
福﨑さんは店舗を引き継いだ当初、前オーナーの時代には赤字だったお店を黒字化することに成功されました。その過程で、単にラーメンを作る技術だけでなく、メニュー表のビジュアル改善や公式LINEの活用など、細部にまで気を配り、常に改善を続けてきたことが成功の鍵だったと感じました。
特に数値管理の重要性を強調されていたのが印象的でした。飲食店経営において「何となく」ではなく、数字に基づいた分析と改善が不可欠だという点は、これから開業を考えている方にとって重要なメッセージではないでしょうか。
また、「コストパフォーマンス」という明確な差別化戦略を持ち、「千円」という顧客心理を捉えたセット設定は、競争の激しいラーメン業界で生き残るための智恵を感じさせます。
ラーメン店を含め、飲食店経営は決して簡単な道ではありません。しかし、福﨑さんのように細部への気配りと改善を怠らず、お客様の立場に立った経営を続けることで、愛されるお店になることができるのだと改めて実感しました。
これから開業を考えている方、現在経営に苦労している方にとって、本インタビューが少しでも参考になれば幸いです。
最後に、お忙しい中インタビューに応じてくださった福﨑さんに心より感謝申し上げます。